📖読んだ本
AI分析でわかったトップ5%社員の習慣(著:越川慎司/㈱ディスカヴァー・トゥエンティワン)
✏️感想メモ
”働き方改革で目指すのは、限られた時間の中でより大きな成果を残し、より多くの報酬や幸せをえること”
❖結果を出す人の五原則
▶目的を考える
・過程よりも結果:経緯よりも結果を重視
・時間を大切にする:オン・オフとも時間を大切にする
・自分で設定した目標を達成する:達成感を大切にする
・仕事は質:目的を正しく理解→目的に合わせた行動→結果に結びつける
▶弱みを見せる
▷好意の返報性:
・話をするうえで相手と腹を割って話す場合、自分もまた腹を割って
話さねばならない
▷自己開示で信頼ネットワークを構築:
・自己開示とは「何の意図もなく自分自身の情報をありのままに伝えること」、
自分の気持を包み隠さず伝えて、相手から共感や理解を得やすくする
▷自己開示の方法:
・イエスかノーかの質問より、自由に答えられる質問をすることでより
多く相手の情報を知る事が出来る
・ちょっとした気遣いと配慮で信頼できる人脈を構築する
▶挑戦を実験と捉える
▷全ては学び、迷った時は苦しい方を選ぶ:
・小さな実験によって自分の行動を帰る経験を得るために、あえて苦しい
選択や難しい選択をする
・1つのスキルや技術に固執することなく、より多様な能力を身に付けて
市場価値を高める
▶意識確変はしない
▷意識を変える前に行動:
・意識を変えて行動するのではなく、行動を変えることで意識が変わる
・「行動を起こすことに価値がある」という意識
▶ギャプから考える
▷目標から逆算:
・目標を設定してから、そこからブレイクダウンして行く
・目的思考の行動派のリーダーは、まずスタートして、途中でチェック
ポイントを設け、どんどん決めていく
・途中でしっかり振り返り、柔軟に行動を修正する姿勢
▷(顧客のニーズを把握する時)相手とのギャップを縮める:
・視野の広さ(全体を俯瞰)
・情報を伝える発表者と効率的に情報を得たい顧客間にあるギャップを、
ニーズを掴んだうえで情報を供給することが出来る
→「問題に対して真摯に学ぶし、新たな知識を得ようとする」
「失敗した時も自分に問い続け、失敗した理由を明らかにして次に活かす」
「失敗をさほど悪いものと考えていない」という一文も好きです。
この原則を見ていくと、無駄なく必要なことをして行く、そのために必要な視点を持つ、視点を持つために経験を重ねる、経験を重ねて自分の勝ちを上げていく、といった「こういう人が仕事出来るんだろうな」っていう人物像が見えてきます。
凡庸な自分にも真似できることは真似して、学べるところは学び、そんな「仕事の出来る人間」に近づいて行けたらと思いました。
❖トップ社員と一般社員はどう違う?
▶限られた時間の中でより多くの成果を残すには、長時間労働を前提にしてはいけない
▶休日の過ごし方:
・好きなことをしたり、運動したり、読書したりする
・本領を発揮するために休む
▶妄想が無駄な資料を生む:
・資料作りを頑張りすぎても結局使われない資料もあり、頑張り分ほどの評価をされない
・評価の対象は「努力」ではなく「成果」
▶眼の前の仕事しか見えてなくて、無駄な仕事をしてしまう:
・目的と進捗を確認する時間を取る→思い違いや自己満足を止められる
▶問題が起きた時:
・①問題発見→②問題分析→③解決策立案の順で問題を整理していく
→今までやっていた作業の中で「本当に必要だったか?」という作業もありますね。心配でとりあえず作ったけど結局使わなかった資料なんていくらでもあります。本当はその時間で、もっと効果的な仕事をしたほうが良かったんだなと今では思います。時間は有限なのです。
❖シンプルな思考と行動
▶デメリットのない挑戦はない:
・成功する唯一の方法は、たくさん失敗すること
・変化に対応していくには、新しいことに挑戦していくしかない
▶完璧を目指さないと楽になる:
・より短い時間でより大きな成果を残す
・「失敗してみると、完璧を目指すのがいかに無意味なことがわかる」(レシュマ・サウジャニ)
▶特定のことを再現できるという状態:
・特定のことが出来る=自身が持つスキルや能力を遺憾なく発揮する
・能力を発揮する考え方と行動を身に付ける
▶手順化・習慣化:
・日々行動を変えていき、振り返って改善する「行動実験」を習慣化する
・改善の欲求がないと成長が止まる
・安定した成功を続けて、さらなる成長を目指す
▶仕事を振り返る時間を作る:
・定期的に内省を行い、次の行動に活かす
・時間は15分~最長30分程度で
▶主体的に行動する:
・主体的な行動→自分発信で周囲を巻き込んで行動できること
・行動力のある人→何事にも好奇心を持ち、新しいことに積極的にチャレンジ出来る人
▶フィードバックをもらう:
・コミュニケーション術を磨きたいなら、(心理的安全性が確保されているという前提で)相手から改善点を指摘してもらった方がいい。たとえそれがマイナスの評価でも落ち込まず、学びを得て次の行動に活かそう。
▶アウトプットの習慣:
・積極的なアウトプットで新たなアイディアやビジネスが生み出される
・思いつき(アイディア)を言語化する
▶結果は準備で決まる:
・成功率を上げるために行動を修正する時間を確保しておく
・やるべきことは「事前に」「漏れなく」把握しておく
→「完璧を目指さないと楽になる」という言葉で肩から力が抜けました。自分ひとりで目指せる完璧にも限界がありますので、人の手を借りてより良いものを作って行きたいと思います。
また「成功するための方法としての失敗」という言葉から、失敗を恐れて何もしないことはより悪いことなのではないか?という思いがふつふつと湧いております。まずはやってみるところから!
❖強いチームをつくる発言
▶摩擦を避けたら成果は生まれない:
・「いい人」は「どうでもいい人」
・摩擦を恐れて波風を立てない「いい人」は「何を考えているかわからない」と思われてしまい、仕事で声がかからなくなったり、活躍の場がだんだんなくなってしまう
・イノベーションの化学反応を起こすためにも摩擦は必要
・完璧にこだわりすぎず、摩擦を避けない
・他人の意見を取り入れ、自分の考えをより良くする視野の広さと冷静さも必要
▶思考停止しないために常識を疑う:
・内省を繰り返し、自分だけの価値観を磨く
・多様なものの見方をして、根拠を探し、自分の価値観と合うか確認する
・読書でも反対の主張をする本を読んで見るとよい
▶感謝はしっかり表現する:
・褒められると嬉しい
・感謝の気持ちは言葉で伝えなければ相手にも伝わらない
▶誰がやるかで揉めるのは生産的ではない:
・会議をしてもその後のアクションを決めないと成果は出ないので、誰がやるかまでのアクションを決めること
・〇〇しよう!と前向きな言動でアクションを決めて会議を締める
▶「もう無理だ」と決めた瞬間にすべて終わる:
・目標達成のために努力していても信じていなければ達成は出来ないので、出来ない理由を考えるのではなく出来るための方法を考えること
▶「ダ行」の代わりに「サ行」を使う
・「だけど」「でも」「ですから」「どうしても」→断定しているようであまり気持ちよく聞こえないし、聞き手にとっても耳障りが悪く、言い訳にも聞こえる
・「そうですか」「そうしたら」「しかし」「失礼しました」「承知しました」→相手の感情を逆なでしない言い方であり、相手の気持を受け止めることにもなる
→時に必要な摩擦もある、という新しい視点を得ました。
また「ダ行」→「サ行」の話では、言葉の音感1つで相手が受ける印象も変わるなら、より柔らかい表現を選ぶことも必要だと思いました。
すぐやる習慣
▶Giveで信頼を高める:
・成果を上げるために「信頼を築くこと」が極めて重要
・相手が動くのは「主張が伝わったから」
・Give→先に相手になにかやってあげること
・Giveすることで良好な信頼関係を築き、困った時にはその相手から支援(Get)を得る〈返報性の原理〉
・一方的にお願いするばかりではなく、得意な分野の仕事を率先して引き受ける行動が必要
▶動きながら考える:
・判断ミス等の失敗は「ある」、ただし早い段階で失敗しているからリカバリーも早いし次の行動に活かして成功率も上げられる(修正力が高い)
・失敗したあとこそがチャンス
・×与えられた仕事だけやる人/○自ら考え行動できる人
・じっとしている人は少し行動を変えてみるとよい
▶新しいもの好きは飽きっぽい?
・好奇心旺盛→次々情報を仕入れる→次々に興味の対象が変わる→新しいもの好きは飽きっぽさでもある
・でもメリット>デメリットなら挑戦するべき
▶報告のタイミングは早く
・締切は守る
・不測の事態が起きた時にはスルーせずに報告すること
・報告は締切が守れなくなりそうな時点で行う
→新しいもの好きが持つ飽きっぽさは確かにありますね。長所と短所は物事の裏表ですが、一見短所でも良いところ・良い部分を見てあげると、それは長所にもなりそうです。
それから後回しにしがちな報告のタイミングは早いほうが絶対いいので、これから報告はすぐすることを心がけたいです。
今日からできるルーティン
▶1日5分、情報収集をする
▶インプットしたらすぐアウトプットする
▶情報が自動的に集まる仕組みづくりをする
▶ざっくばらんに相談できる先輩のような存在(メンター)にアドバイスをもらう
▶「自分で決める・選ぶ」という行為が自分の幸福度を高める
▶師匠としての「マスターメンター」を決めて、じっくり観察して真似する→成長への近道
▶思考停止を恐れる
▶社外にも人脈をつくる
▶人脈づくり5ステップ
①新しい人に会う
②何かを提供する
③信頼を高める
④仕事で関わりをもつ
⑤人を紹介してもらう
▶内省タイムで行動改善を
▶定期的に振り返り、考えるクセを付けて自分で問題を解決できるようにする
→この人のようになりたい!という「師匠的な人」を決めて、その人をじっくり観察して、いいところを真似て行きたいと思います。
「自分で考えるクセ」は今よりももっと磨いて行きたいです。
あとがきより
▶目指すべきは「働き方改革」ではなく「稼ぎ方改革」
▶労働時間を減らして浮いた時間をスキルアップ等に充てれば変化への適応力が上がる
▶成功パターンを実践する
▶「自己選択権」は人を幸せにする
▶本を読んだ方にも適用できる行動パターンはあるはず、なんでもいいからどれか1つ試してみてほしい
▶【この読書の目的は「知ること」ではなく、「行動すること」です】
✏️おわりに
この本を読んで、「働き方改革っていうけど、実際効率的にやっても自分の仕事が増えるだけでは?」と思っていたのですが、労力を減らしつつ仕事が増える→自分のスキルが上がる→収入が増えるといった「自分のスキルアップにも繋げていけそう」と思いました。
そのためには「他人の力」が必要ですし、「他人の力」を借りる・助けてもらうことも大切なようです。そして困ったときに助けてもらう・力を貸してもらうためには「こちらから先に相手になにかやってあげる(Give)」が必要で、会社の中でもGiveして相手と良好な関係を築くこともまた大切だと思いました。
私は仕事における摩擦を避けてきたのですが、必要な摩擦もあるという新しい視点も得られました。「いい人」は「どうでもいい人」という言葉は自分のこれまでやってきたことについて改めて考える機会にもなりました。積極的な摩擦を起こしていくなんてことではなく、なにか新しく生み出すための摩擦を恐れず仕事をしていきたいです。
また、失敗を必要以上に恐れる必要もなさそうです。どちらかというと、失敗を次の成功に活かせていけるなら、時に失敗も必要だと感じております。
この本は、人事評価の上位5%の人たちの働き方を徹底的に調査して、行動や発言を記録し、分析した結果から5%社員の共通点と、それ以外の社員との違いをまとめた1冊です。
仕事が出来る人たちの習慣や行動を真似できるところから真似してみると、自分に足りなかったものや、こうした方がより良くなるという方法が見つかって行くのかなと思いました。
上位5%の社員さんがやっていることは分かったので、次はこちらが行動するだけです。失敗も計算に入れながら失敗を恐れず行動して、今よりもより良く、効率的に仕事が出来ていけたらなと思えた1冊でした。
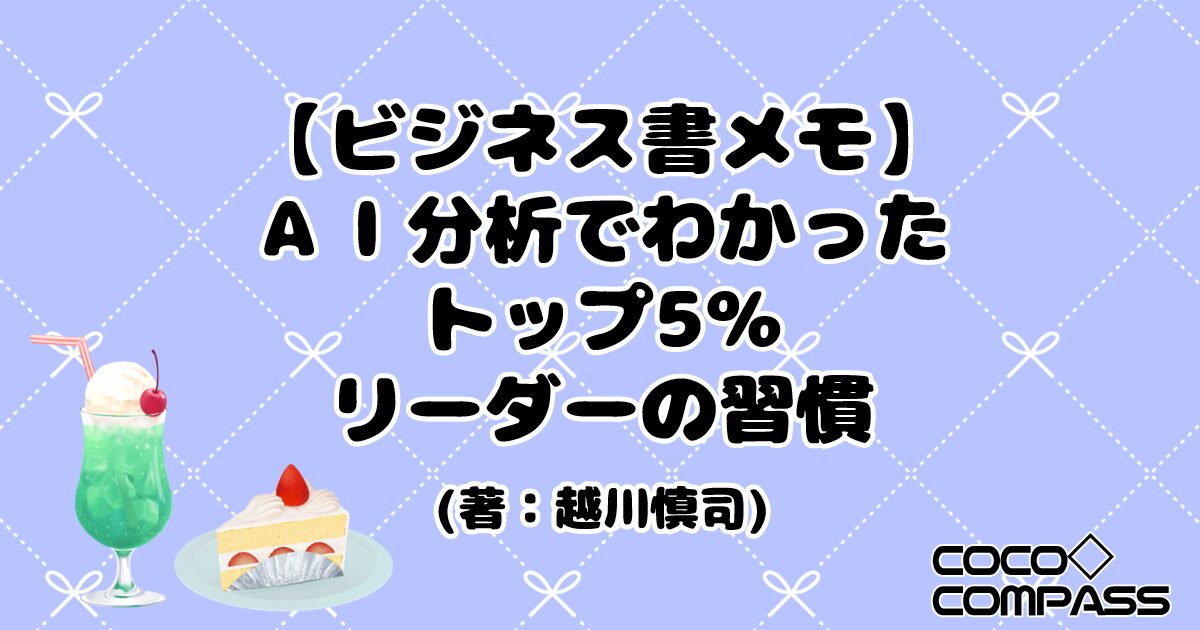
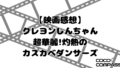
コメント