3人のおばば、少女を育てる
(読んだ本)姥玉みっつ(著:西條奈加/潮出版社)
亀の甲より年の功!
こんな話
主人公の「お麓」は名主からの仕事の依頼で「おはぎ長屋」に越してきたところ、幼馴染の「お菅」と「お修」も同じ長屋に引っ越してきて、主人公の生活は彼女の望む静かなものではなくなっていた。
そんな望まない賑やかな生活を送っていた中、長屋の裏手の萩の原で人が倒れているとお菅が家に駆け込んできた。その場に向かうと足に怪我をした母親とそばに娘が。一悶着ありながら、結局主人公が親子を家に預かることにしたが、ほどなくして母親は亡くなってしまう。
母親が亡くなってしまい娘の今後をどうするかを話し合ったものの、娘の方は口を利くことができないようで身元が分からない。身元が分からなければその後のその子の身の振り方も決められない。そこで、母を失った娘を「お萩」と名付け、お麓・お菅・お修の3人でお萩の面倒を見ることになるのであった…
感想
主人公のお麓の望む、できれば静かな変わらない日々を変えたのは、お修であり、お菅であり、お萩でした。
どうにもお萩ちゃんが世間慣れしていないことを心配し、家事をお菅さん、手習いをお麓さん、町案内をそれぞれ教えることになりました。教えたことをめきめき身に付けるお萩に3ばば様は鼻高々です。お萩ちゃんの里子の申し出を突っぱねたり、正月の身内周りを4人で巡って楽しい正月をすごしたり。
ただお萩ちゃん、出会った時に一見貧しい身なりをしていたものの、仕草はどうにも町民や農民のそれではありませんでした。そしてそれを悟らせないような様子も見えます。この「子どもらしくない用心さを持つ子供」お萩ちゃんに対して「そうさせたのは大人の悪意ではないか?」と3ばば様たちは疑問を持つようになりました。
物語の終盤、喋れるようになったお萩ちゃんの口から知らされることの真相は重く、3ばば様始め、長屋の皆さんやこの作中で広がった人の輪を通して問題解決への道を探していくことになります。
人生の酸いも甘いも味わい尽くしてきた3人のおばば。老後と言って差し支えない3人の生活は、それぞれに問題を抱えていながらも穏やかでかしましく楽しそうでした。
お修さんの後入のお家での義娘と確執、お菅さんの嫁と姑の関係の話、お麓さんの家族の話は、どこか人ごとではないような、身近な話題のように感じました。
それからこの3ばば様、割とケンカします。それは自分の生き方と意見がちゃんとあるからで、目的は相手をけなすことではありません。相手の意見に聞くところがあればちゃんと聞きますし、相手の意見に違うと思うところあればしっかりそうと伝えます。
気に入らないところは気に入らないと言うけど、認めるところはちゃんと認めている。古い幼馴染同士、あまり言いたいことを我慢しないのも、この関係の良さの賜物でしょうね。
あと、お菅さんとそのお嫁さんの話があるのですが、いわゆる「古い家の考え方」も、せいぜい明治以降の考え方なのだろうな、と思いました。
好きポイント
「誘われているうちが、花ってもんさ。構ってくれる者がひとりもいないなんて、寂しいじゃないか。年寄りなら、なおさらね」という、お修さんのセリフにハッとします。
私も誘われるのは面倒に思ってしまうタイプなのですが、誘われなくなったらそれはそれで寂しいものです。「誘われているうちが花」と思って、行ける時には誘いに乗りたいと思いました。行けば行ったで、楽しんでしまうんですけどね。
お萩のために和歌の見識を広げようと、和歌の座に足を運ぶお麓さん。今までの彼女ならいかなかったであろう場所に行き、そして人と出会い、人の輪は広がっていきます。自分から一歩踏み出せる、新しい世界へ飛び出していけるお麓さんはすごいと思いました。
終わりに
朝からばっちりお化粧で余念のないお修さん、過ぎるほどのおせっかいを焼くお菅さん、人付き合いに淡白な皮肉屋のお麓さん。3者3様の人生を送ってきてたどり着いた今の時間を、彼女たちはとても楽しそうに暮らしています。時々ケンカしながらも、それでもきっとこれからも、彼女たちは笑って楽しく暮らしていけると思いました。
生きていて良いことばかりではないけれど、悪いことばかりでもない。たくさん経験を積んだ先、年を重ねたその先の人生も、そんなに悪いことばかりじゃない。そう思えた1冊でした。
今日はここまで、それではまた別の本で。
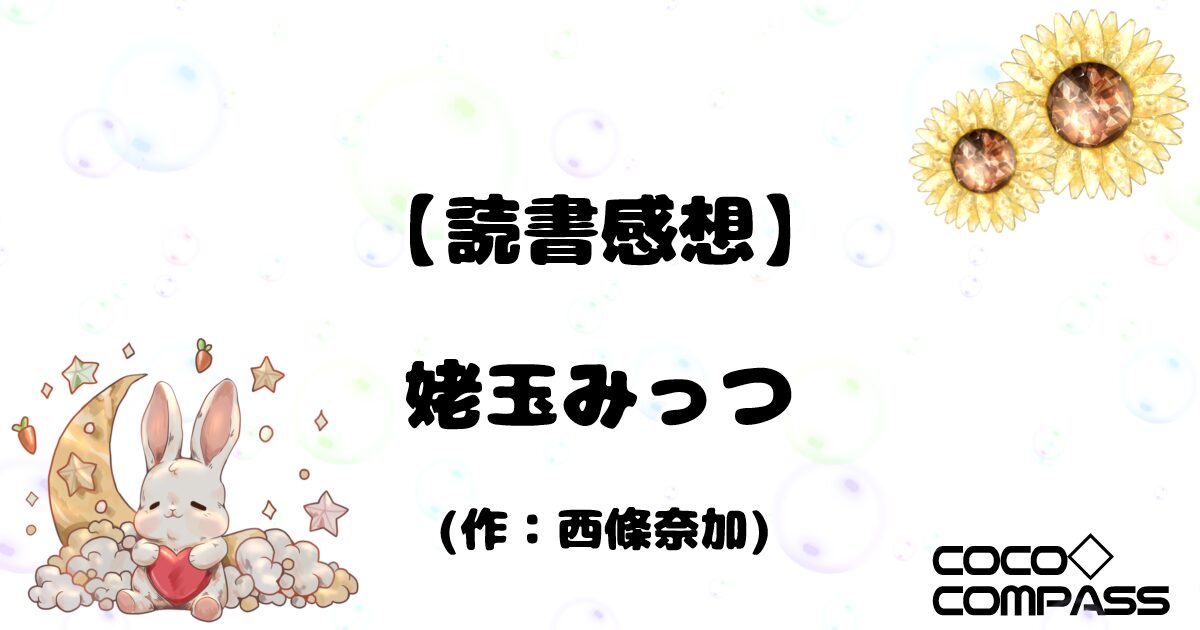


コメント